当ブログはアフィリエイト広告を利用しています
被災地の皆さまが、一日でも早く日常を取り戻せる日が来るよう、心よりお祈り申し上げます。
2024.10.25(金)
最高気温 23℃、最低気温 18℃
こんにちは、レトです😊
2週間ほどブログをお休みしておりました。
この間に見に来てくださった方、ごめんなさい🙇💦
引き続きよろしくお願いいたします😊
さて、季節は進み、今は秋の土用(10/20~11/6)ですね。
全然知らなかったのですが、この土用の期間は土いじりをしてはいけないと知りました・・。
( あ、それでお休みしていたわけではないです^^)
たまたま目にしたニュースで、
Q: なぜ、土用の期間に土をいじりをしてはいけないの?
土を司る神様の土公神(どくじん)という神様は、時期によって居る場所が違い、土用(の期間)は土に宿ると言われています。 この土公神という神様がゆっくりしていたいのに土をいじると怒り、祟りを起こすと言われているからです。
具体的には〈土いじり〉〈草刈り〉〈草むしり〉〈地鎮祭〉〈建築の基礎工事〉〈造園〉〈穴掘り〉〈井戸掘り〉などです。
ただ、この期間には間日(まび)いう日があり、その日は土いじりをして良いと言われています。
( 今年は、10/22、10/24、10/26、11/3、11/5が間日です。)
というのを見つけてしまいました。
「わぉ・・。知ってしまったからには、どうしようかな。。」と。
ちょうどビオラの植えつけや、ラナンキュラスラックスの株分けをしようとしていたので、間日を狙ってやろうかと思っています。
「でもな、、それだとできる日が無いじゃん・・。」とも。
みなさんはどうされていますか?
知ってしまうと気になるタイプです💦
では本題に😊
今日は、ヒューケラのコガネムシ被害のお話です。
秋になり、「そろそろヒューケラを日向に戻そうかな?」と思っていたところ、様子のおかしいプランターを発見💦
放っておくと最終的には枯れてしまうので、急いでレスキューをしました。
レスキュー後、土を処分しようとひっくり返してみたら、案の定、コガネムシ(の幼虫)がいました。
今日は、その発見の仕方と、レスキュー方法、挿し木で復活させた様子をご紹介させていただきます😊
コガネムシの写真は出てきませんのでご安心ください😊✨
【 見つけ方 】コガネムシがいるサインはコレ!

2024.9.30撮影
↑ こちらがコガネムシ被害にあった(あっている)プランターです💦
この姿を見て、「あ、しまったー。やられてる・・・💦」と。
実は去年、初めてこれと同じ姿を、スーパートレニアカタリーナで経験しています。
よく見ると、土が濡れているのに葉っぱがクタっとしていますよね?
他のヒューケラ達と一緒に、同じ場所で同じように水やりをしているのですが、この子だけ水を吸えていません💦
こんな風に、「秋のこの時期に、水やりをちゃんとしているにもかかわらず、クタっとしている」というのは、コガネムシの幼虫が土の中で根っこを食べている可能性大です💦
根っこが食べられているので、水やりをしても水を吸える根っこが無い・・。
オルトランを定期的にあげていれば良かったです。反省・・。

2024.9.30撮影
↑ 葉っぱを軽く持ち上げただけで、すっぽりと抵抗なく株が抜けてしまいました。
案の定、根っこも付いてきません💦

2024.9.30撮影
↑ 植えていた2株とも、あっさりと取れてしまいました💦

2024.9.30撮影
↑ 裏を見てみるとこんな感じに。
カッターでスパッと切ったように、白い軸が見えています。
根っこを全部食べるんですね💦
この後、プランターをひっくり返し、土の片づけをしました。
中にはやっぱりコガネムシの幼虫が・・💦
去年は初めての経験だったので、「ギャー」っと叫び、
今年は2回目なので、「ハイハイ。居るのは知ってるわよ」と(笑)。
来年は手で触れそうな勢いですが、もううちの鉢植えには住んで欲しくないです・・(笑)。
【 挿し木で 】まだ間に合う!コガネムシ被害からの復活方法

2024.9.30撮影
↑ さて、気を取り直して(笑)、ここからはヒューケラの復活方法です。
ヒューケラだと、根っこの無い状態から根っこを出させることが可能なので、気づいたのが遅すぎなければレスキューできます✨
挿し木で増やす場合も、同じ「根っこ無し」の状態からスタートするので、レスキューも同じ方法で挿し木にして、根っこが出たらまた鉢植えにしたいと思います😊✨
上の写真は、さっきの取れてしまった2株を掃除したところです。
枯れ葉を取って、元気な葉っぱだけにしようとしたら、自然と4つに分かれてしまいました。

2024.9.30撮影
↑ 葉っぱを見るとこんな感じです。
しおれておらず元気な葉っぱなので、「復活の見込みあり」だな、と感じました💪✨

2024.9.30撮影
↑ 株元のアップです。
見えている、黒いカリカリした部分の下(内側)から新しい根っこが出てきます。
( 黒い部分は後で削り取ります。 )

2024.9.30撮影
↑ 挿し木にするので、まずは葉っぱを減らしておきたいと思います。
根っこが無いので、葉っぱは2枚ほどで充分かな、と。
せっかくある葉っぱですが、外側から葉っぱを取っていき、2枚だけの状態にしました。

2024.9.30撮影
↑ そして、黒い枯れている部分を爪でカリカリして取っておきます。
白い部分が少し見えればOKです😊✨
これで、発根がスムーズになります。

2024.9.30撮影
↑ 4つとも同じようにしました。
これで挿し穂の出来上がりです✨

2024.9.30撮影
↑ 挿し穂は水に浸けて、乾燥しないようにしておきます。
今日はこれでタイムオーバーなので、作業の続きは翌日に。
室内に入れ、このまま次の日まで水に浸けておきました。

2024.10.1撮影
↑ 翌日です。
挿し木していきます。
用意するのは、小さめのビニールポットと挿し木用の土です。
(ビニールポットは直径6cmのもの。挿し木用の土はセリアのものを使っています😊)

土は、栄養の無い土ならOKです。
専用の土を買わなくても、赤玉土や鹿沼土などで代用できます😊
粒の大きさは、小粒や細粒がおすすめです。
濡らした水ゴケでくるんであげる方法もあります✨

2024.10.1撮影
↑ ビニールポットの中に鉢底ネットを敷き、挿し木用の土を半分の高さまで入れ、

2024.10.1撮影
↑ 挿し穂を載せます。
( 挿し穂が小さいので、1ポットに2本挿す事にしました。)

2024.10.1撮影
↑ そのまま土を流しいれ、

2024.10.1撮影
↑ 挿し穂を真っすぐ起こし、土を押さえてしっかり立たせます。
土を入れ終わってから挿し穂を挿すより、この方が茎が折れる心配がないので安全です😊✨

2024.10.1撮影
↑ ここで発根のお手伝い、「リキダス」の登場です。
挿し木の成功率をあげたいので使うことにしました💪✨
(*リキダスが無くても、発根する子は発根します😊)

2024.10.1撮影
↑ 規定量の水で薄めたリキダス水で水やりします。
「前日の水もリキダス水にすれば良かったかもな」と、今更ながら気づきました。

2024.10.1撮影
↑ 水やり後、再度土を上から押さえて、株をしっかり立たせ、完成です✨
土がしっかり濡れていない可能性もあるので、翌日まで腰水しておくことにしました。
これで発根を待ちます。
3~4週間?もっとかな?
発根まではだいぶ時間がかかると思うので、気長に待ちます✨
挿し木苗の置き場所と水やりは?

2024.10.1撮影
↑ 置き場所は、気温が安定していて、ほぼ無風の場所であれば、こんな風に日陰の屋外の場所でも大丈夫です。
最初は、「ここで育てようかな」と思って置いていたのですが、数日後、家の中に取り込みました。
すごく晴れたり、風が強い時もあったので、「ちょっと厳しいかな」と。
気温差があまりなく、風も強く吹かない室内が安全ですね😊
3週間経ちますが、今もずっと室内で育てています。
室内での置き場所は、日の当たらないやや暗めの場所にしています。
(曇りの日は、窓辺においてあげる時もあります)
水やりは、最初の2日だけ腰水し、それ以降は土の表面が乾いた時にしています。
( リキダス水は、水やりの3回に1回くらいの頻度で使っています。)
【 レスキューしたヒューケラ 】3週間後の様子

2024.10.21撮影
↑ こちらが今の様子です。
撮影するので外に持ってきました。
やっぱり太陽に当たっていないと、葉っぱの色がどんどんくすんできますね・・。
でもしょうがない。
株自体は元気そうなのでOKです😊

2024.10.21撮影
↑ 株を軽く引っ張ってみると、「抵抗があるような、無いような・・・」。
微妙に根っこが出ているのかもしれません😊
土の中は見れませんが、株元には新しい赤ちゃん葉っぱが出てきているので、レスキューは間に合ったみたいです✨
引き続きこのまま室内で育て、根っこが出たら窓辺に移動、さらに数か月経ったら屋外に移動して、ゆくゆくはまた鉢植えにしようと思います。
これで今日のレスキュー方法は終わりです✨
【 あると安心😊お花の薬剤・活力剤 】私が使っている5つをご紹介

こちらは私がいつも常備している薬剤です。
薬剤の使用をお勧めしているわけではありませんが、
植え付け時だけでなく、急なトラブルが起きてもすぐに対処できるように薬剤を準備しています。
予防や早めの対処でお花を守れます✨

↑ こちらが私がいつも使っている薬剤4種類です。
☑ 写真左) オルトランDX粒剤 主に虫の対策に使用
☑ 写真左から2番目) ハイポネックス液体肥料殺虫剤入り 液肥に殺虫剤が入っているタイプ
☑ 写真右から2番目) ベニカXガード粒剤 虫と病気の両方を対策できる粉末タイプ
☑ 写真右) ベニカXネクストスプレー 虫と病気の両方を対策できるスプレータイプ
* 使い分けとしては、虫対策だけをしたい時にはオルトランを使っていて、
病気(特にうどん粉病)も心配な植物を育てる時は、植え付けの時に予防としてベニカXガード粒剤をまき、その後、病気が出てしまった時に、ベニカXネクストスプレーをスプレーしています。
* ハイポネックス液体肥料殺虫剤入りも便利です。肥料やりと殺虫が同時にできるので、虫の発生と肥料やりのタイミングが同じの時に使っています。
どれも守備範囲が広いので😊、常備していると早めに被害を食い止められるので安心です✨


【 ~ PRです ~ 】
PRになりますが、雑草対策はみなさんどうされていますか?
「自分でやるのはちょっと・・」と外注したい場合は、
こういった業者さんもありますのでご参考にしてください😊
「自分でやった場合」との料金比較も出来るかと思います✨
↑ こちらは、
☑ 防草シート張りも頼めます。
☑ 東証上場企業が運営(シェアリングテクノロジー株式会社)
☑ 相談・見積り無料で、見積後のキャンセルも無料です。
☑ 「1坪あたり390円~」で、見積もり後の追加料金が発生しないとの事です(※別途出張費3,000円がかかる場合があります)。
↑ 同じ会社さんです😊
「砂利」というと、和風なイメージが強いかもしれませんが、化粧砂利や白玉砂利をはじめ数々の種類をお持ちで、お庭だけでなく「駐車場や家の周りに敷きたい。防犯対策をしたい。」といったニーズでご利用される方もいらっしゃいます。
実際、ホームセンターを往復して玉砂利を買うのは時間がかかり、何より重くて運ぶのが大変でした・・💦
これで今日のブログは終わりです😊
最後までお読みいただきありがとうございます。
読んでくださった方のヒントとなれば嬉しいです。
新しいブログの更新は、金曜日の夜20時です。
( 毎週アップできない時もあります。その時はごめんなさい🙇。翌週にまた見に来てくださると嬉しいです。)
引き続きよろしくお願いいたします😊✨

これまでにご紹介した記事は235になりました。
これまでの記事一覧は、サイトマップからご覧いただけます♪
お花を探す時などにお役立てください^^
(サイトマップへは、トップページからお入りいただけます)
よろしくお願いいたします。



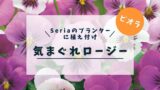


コメント